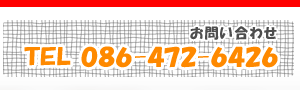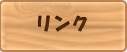宮沢賢治
趣味の項目にあげてしまいましたが、おかしいですね。彼の童話や短歌は大変好きなのですが、すべてが好きかと問われると、はっきりいって、よくわかりません。
詩についてはさらに敷居が高い気がします。「春と修羅」などはかなり手強い。「永訣の朝」[松の針」「無声慟哭」でとし子が死ぬところは泣けて泣けて仕方がなかったですね。
全体的には僕の頭ではとてもついていけないところが多々あります。感受性と想像力が桁違いです。それも何桁も。
板谷栄城氏は「賢治は人間の悲しさやさびしさといったものに対して、人一倍深い感受性を持っていました。また、自然の美しさやすばらしさに対しても、並外れて鋭い感覚を持っていました。それは詩人として欠くことのできない資質ですが、真の超天才的な詩人の場合は、それだけでは十分といえません。では何が必要かというとそれは普通の人が感じることのできない美しさを感じ、思うことのできない悲しさを思い、見ることのできない不思議を見るという、天与の特別優れた感性です。このような感性を備えた人のことを、ボワイヤンとといい見者と訳しますが、フランスの詩人ランボーはその代表的な一人です。しかし、ランボーをして彼を遙かに凌駕するのが賢治である」と述べています。
賢治はこう言っています。
「注文の多い料理店」の”序”から
「(中略)これらの私のおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらってきたのです。
ほんとうに、かしわばやしの青い夕がたを、ひとりで通りかかったり、十一月の山の風のなかに、ふるえながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたがないのです。
ほんとうにもう、どうしてもこんなことがあるようでしかたがないということを、わたくしはそのとおり書いたまでです。
ですからこれらのなかには、あなたのためになるところもあるでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、わたくしには、そのみわけがつきません。なんのことだかわけのわからないところもあるでしょうが、そんなところはわたくしにもまた、わけがわからないのです。
けれども、わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまい、あなたのすきとおったほんとうのたべものになることを、どんなにねがうかわかりません。」
それはともかく、彼の童話で一番好きなのは「やまなし」です。透明で美しく、幻想的です。しかもわかりやすい。このような視点でものを書いた人がいるでしょうか。
賢治のことを知れば知るほどあれほど純粋に生きた人が本当にいたのかと信じられない思いがします。
ところで、”やまなし”に出てくる「クラムボン」とはいったい何だろうという賢治研究家の論争があります。「新宮澤賢治 語彙辞典(原 子朗、東京書籍)」によるとたくさんの諸説がありますが、「文意からは、泡の様子や、水面の反射光等の擬態語とも考えられる。だが、この童話では、そうした語意の追求よりも、あたかも水の流れや反射光の微妙な変化と躍動が直接伝わってくるような、語感の響きの妙を味わうべきだろう」と結んでいます。私もそう思っているのですが。
賢治の青の心象
賢治は青い色や青い光をたくさん使っています。これでもかこれでもかという感じです。もちろん青だけでありません。黄色、そして光。
板谷栄城氏は「宮澤賢治の見た心象」の中でそのことは寂しい気分がどうのこうのといういう、三次元的な色彩心理学の説く理由からではありません。しばしば自分が見た青い心象があまりにも強烈だったので、それを念入りに何度も書いたに過ぎないのです。」と書いています。
また、すざまじい悲しみを次のように表現しています。
それは全く熱いくらゐまで冷たく
味のないくらゐまで苦く
青黒さがすきとほるまでかなしいのです。
なくなった妹を偲んで書いた「風林」には
としことしこ
野原に来れば
また風の中に立てば
きつとおまへをおもひだす
おまへはその巨きな木星のうへに居るのか
綱青壮麗のそらのむかふ
(ああけれどもそのどこかも知れない空間で
光の紐やオーケストラがほんたうにあるのか)
賢治の死の予感と不安
昭和3年(1928)東北地方の大干ばつに見舞われ、農民は大変苦しい状況に追い込まれ、賢治はその対策のためにかけずり回っていましたが、8月に入り疲労で倒れてしまいます。その後花巻病院で両則肺浸潤と診断され、自宅で療養することになったのです。以後めっきりと体力が落ちてしまいました。賢治はトシの命を奪った結核にとりつかれてしまったのです。
昭和4年(1929)に入り、賢治の病状は一進一退を続けていました。様態が急に悪化することはないものの、精神的な不安ですっかり参ってしまったようです。
その頃、書きかけて中断した詩句に、こんなものがあります。
「そしてわたくしはまもなく死ぬのだらう/わたくしといふのはいったい何だ/何べん考へなほし読みあさり/さうともききかうも教えられても/結局まだはっきりしてゐない/わたくしといふのは」
かつて「春と修羅」の序で「私といふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」と書いた賢治は、このころ、自分というものを見失ってしまったのでしょう。
※イーハートーヴ:文学作品の舞台としての岩手の風土のことをエスペラント語風にもじって名付けた。