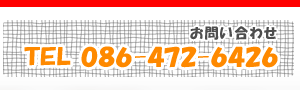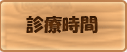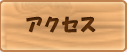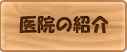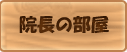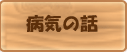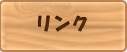ブーゲンビリア
街のあちこちに紅い塊がかがやいていた。ブーゲンビリアである。少し前の夏、北イタリアのサンタ・マルガリータ・リグレを旅したときのことである。花びらに見えるのは葉の一種である花苞(かほう)で、中心部にかわいらしい白い花を持つ。
紺碧のリグリア海に面したこの小さな街の緯度は札幌と同じくらいである。冬はかなり寒くなるだろうに、中南米原産のこの植物が生きていけるのかと不思議だった。しかし、この地はアルプスが冷たい空気を遮断するため、温暖で住みやすいところで、イタリア人がリタイア後に余生を送りたいと考える、とても人気のある場所だそうだ。南国のような明るくてとても美しい街だった。植生も違うのだろう。
ブーゲンビリアのほかにキョウチクトウ、サルスベリなどが街を彩っていた。ほとんどがピンクの花だった。
 碧く澄んだ海、でこぼこの石畳、古めかしい鉄のランプ、ピンクや黄色の壁、愛すべきオレンジ屋根、グリーンの窓、テラコッタの鉢、窓辺に飾られた赤い花達、これらすべてが調和していた。イタリアの街は絵のように美しい。特に色使いがすばらしい。そして人々は昔からの伝統を守り、頑固なまでにその美しさを維持していこうとする。残念なことだが、このあたりが日本とはまるで違う。
碧く澄んだ海、でこぼこの石畳、古めかしい鉄のランプ、ピンクや黄色の壁、愛すべきオレンジ屋根、グリーンの窓、テラコッタの鉢、窓辺に飾られた赤い花達、これらすべてが調和していた。イタリアの街は絵のように美しい。特に色使いがすばらしい。そして人々は昔からの伝統を守り、頑固なまでにその美しさを維持していこうとする。残念なことだが、このあたりが日本とはまるで違う。煉瓦作りの駅舎とブーゲンビリアの写真を撮ったつもりが、その樹はキョウチクトウだった。その後訪れたトスカーナ地方の木々を注意深く見て歩いたがブーゲンビリアは1本もなく、ほとんどがキョウチクトウかサルスベリだった。あれは本当にブーゲンビリアだったのだろうか。
おととし、ピンクと紅色の2鉢のブーゲンビリアを買ってきて無謀にも地植えをした。始めはきれいに咲いていたが、ピンクのものは秋を待たずに枯れ、紅色の方は気温が下がるにつれ、あたかも狂い咲きしたかのように鮮やかに色づき、あっという間に枯れた。
生息地では開花は一年中というが、やはり寒さには弱いのだろう。やはりこの地で地植えをすることなど不可能なのだ。
まばゆい光が似合う花で、特に空と海の青に映える。沖縄の海辺などに咲いている姿は明るく爽快だ。塊の樹と称されるようにこんもりと花をつける。
セルロイドに美しく色づけをしたような苞は蝶々の羽のように明るく奔放であるが、この樹、実は気むずかしい。花のすぐそばには鋭い棘が近づくものを拒んでいる。棘はとても長く、戦闘的である。守らなければならないものが多いのかもしれないが、それが僕にはとても魅力的だ。
枯れた樹を片付けていたら、指先に鋭い痛みを感じた。枯れてもなおの復習の一撃だった。今度は鉢で挑戦してみることにしよう。
(児島医師会報 2010年掲載)