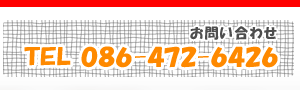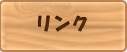埴岡先生は型破りな小児科医だった。風貌はゴリラさんに近かった。時々寂しくなった頭を後ろになでて「イヤァ、ハッハッハッ」と笑った。
先生は毎朝、医局のソファにどっかりと座り、ゆっくりとピースに火を付け、とてもおいしそうに吸いながら自分でインスタントコーヒーを作って飲んだ。先生はタバコとコーヒーが大好きだった。いつも朝食抜きだったので、コーヒーは先生のスタミナ源だ。コーヒーの粉末を入れ、砂糖をモーニングカップに半分ぐらい入れ湯を注いだ。まるで砂糖壺にコーヒーを入れているかのようだった。
外来には朝5時頃から患者さんが弁当持ちでやってきて待っていた。先生はそれをちらりと見て、9時に病棟にあがり入院している子どもたちの診察をした。先生は長い間一人で外来も入院もこなしていたので、入院の子どもをまず診ておかなければならなかったのだ。先生が院長になったため、部下が必要になり僕が派遣された。医者になって2年目だった。
先生は入院患者を診た後、検査や治療の指示をした。必ず採血があり、ほとんどの子どもを自分で採血した。当然のことながら血管を全く見ることも触れることもできない子どもが必ずいたが、ほとんど採血した。よく「わからん血管から取れるかどうかが大切なんじゃ」とおっしゃっていた。採血できなかった子はいなかったと思う。すばらしい技術だった。
病棟の仕事を速やかにすませ、外来に下りた。朝10時過ぎごろから診療開始だ。「外来は戦場だ」「怖いな」が口癖だった。
診察室は騒然としていた。カルテが飛びかっていた。子どもの泣き声がはじけ、先生の罵声が飛んだ。指示がバンバン飛び、「ハイッ」「ハイッ」とナースと事務員が走り回った。今では信じられないかもしれないが、診察机の横のベッドで浣腸され、先生の隣でそのまま便器の上に座ってがんばっていた子どもがいた。珍しくない風景だった。当然、臭いもきつかった。それに机の上にはピー缶がおいてあり、先生は時折診察中に煙を上げていた。
そして、先生はがんがんおかあさんを叱った。「こんなことじゃダメだ。」「何をしていたんだ。」おかあさんは泣いた。
叱り方は厳しく徹底していた。しかし、子どもたちにはいつもとても良い笑顔を見せた。時折メガネの上から愛嬌のあるギョロ眼をのぞかせ、にこりとした。ゴリラさんが笑ったら、とてもかわいかった。子どもには本当に優しい人だった。
先生はどんなに忙しくてもきちんと診察した。ここに肺炎があると言い、レントゲンを撮ってそれを証明した。ある先輩は神業だと言った。
カルテが舞い散り終わるのが3時頃だった。昼食をさらりとすませ、そのまま乳児検診へ。乳児検診は5時頃終わり、また病棟へ。
入院患者を診終わると卓を囲んだ。先生は麻雀が大好きだった。区切りが来て、誰かが止めたい様子を見せても先生は止めようとはしなかった。特に負けているときには絶対止めようと言わなかった。とても負けず嫌いだった。
ある時僕は先生に誘われ、飛鳥に旅することになった。先生は考古学が大好きだった。連休前の金曜日に仕事が終了した後、車で出かけることになった。先生は車を飛ばすのが大好きだった。先生は夜の国道をガンガン飛ばした。古い三菱ギャランをギャンギャン走らせた。どこかの山越えのカーブにタイヤをギャーギャー泣かせた。おまけに古いギャランはサスペンションがフワフワでよろめきどうしだった。また後ろの車に抜かれると絶対抜き返した。先生は人が変わるのだった。僕は生きた心地がしなかったが、その時の恐怖を不思議と覚えていない。
無事、夜中にホテルに着き、先生と共にツインの部屋に泊まった。夜も更けていたので僕は寝ることにしたが、なんと先生は本を読み始めた。考古学の本だ。先生は本が大好きだった。夜寝る前に本を読まないと寝られないのだ。僕は先生が何時に寝たのか知らない。
翌日、元気いっぱいの先生と飛鳥の古墳を見て回った。いろいろ教えていただいた。恐ろしく博学だった。
その後もう一度、先生と奥様と僕の妻と長女とで正倉院の蔵出しを見に行った。長女をとてもかわいがってくださった。 ある時先生は腹痛を訴え、急性肝炎を起こし入院した。大学からピンチヒッターの先生方が来られ、なんとかしのいだ。先生はじっとしているのがとてもつらそうだった。
その後元気に復帰され、いつもの生活が始まったが、タバコも砂糖コーヒーも昔のままだった。
2年後、僕は大学の教授から新居浜に転勤を命じられた。先生は「がんばれよ」と送ってくださった。僕は先生に「お体に気をつけてください」と言った。
新居浜にいたとき、先生の訃報を聞いた。朝車で出かけたとき、心筋梗塞の発作を起こし、即死に近い状態で運ばれたということだった。飛んで帰り葬儀に出た。涙が止まらなかった。棺にかじりついて大声で泣いた。
僕は先生が大好きだった。あの笑顔が大好きだった。
先生は自分の生き方を貫いて亡くなった。医者の不養生そのままの先生はあまりにもその通りに逝ってしまった。
先生には本当に多くのことを教えていただいた。
どんなに叱られてもどんなに待ってもおかあさんは先生の診察を受けに来た。まるで、叱られに来ているかのようだった。おかあさんたちは先生の子どもたちに対する愛をしっかりと感じていたのだ。僕はこれこそが神業だと思っている。
しかし、僕にはこれをどうしてもまねできない。
(2001.5)