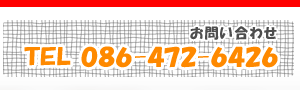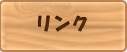無花果(いちじく)
倉敷の町中を歩いていたとき、旧家の庭先の無花果が目に入った。立派な庭に無花果の木があることに驚いた。木の姿はお世辞にも美しいとも思えなかったが、実を楽しむのだろうか。
こどもの頃、家の隣は豊かな農家で大きな無花果の木があり、瓦土塀の上から無愛想に葉をのぞかせていた。秋になるとたくさんの実をつけた。
この季節、家に帰ると、隣家の老婦人から頂いたこの不気味な果実がお皿に盛られていた。山盛りの無花果たちはなんだか揚げられる前の鶏の足に見えた。お尻が割れ、赤い内臓が見えた。さらに僕を不安に陥れたのはちぎられた茎のところからじわりとでてくる白い樹液だった。皮膚がかぶれると信じていた僕はいったいどうやってこの不気味な果実を食べたらいいのか分からなかった。
白い樹液が手につかないように細心の注意を払ってべたべたしながらむずがる薄皮を剥き、指が食い込むのをおぞましく感じながら目をつぶって口に入れた。グニュッとして、すぐにねっとりした甘さが口の中に広がった。水っぽいものが多かったが、1〜2個を口にほおばり、それでおしまいにした。
まだその頃は田んぼが多く、畦道の端々に無花果の木が植えられ、秋になると一斉に実をつけていた。もちろん取って食べた覚えはない。あの白い樹液がいやだったのかもしれない。昔はいぼにつけていたというこの液は消化酵素が含まれているということだが、いかにもかぶれそうだった。
花が咲くことなく実がなるというのでこの字が当てられたが、花も実も実の形をした花嚢の内にあるそうだ。ことばの姿から、趣があるのか古い文学作品にも良く顔を出しているが、その存在感は果てしなく軽い。
田んぼの端に植えられた無花果の木はたくさんの実をつけ、近所に配られるか、そうでなければ多くは放置されていた。晩秋の柿のように。古い土塀に黄色の実だけが綿花のような柿の実。鳥さえもついばんでくれないという悲しさにあふれるが、その寂寥感が郷愁を呼び覚まし美しくさえある。しかし、無花果にはそのような詩情とは無縁だ。
皿に盛られた無花果達、それを見たときの軽い失望感が今も心の底に澱のように残る。ときに美味しいと思うこともあったのに。
しかし、最近では完熟いちじくといって本当に手をかけられた美味しいものが作られているらしい。確かに、最近無花果に対する印象が変わってきた。世界中で食べられているようだ。イタリアの市場でもそのままの無花果が売られていた。フランスでも高級なフレンチの食材として食べられているそうだ。なんと日本料理にも。
さらに、ポリフェノールやらペクチン、抗ガン作用がある成分、エストロゲン成分などいろいろ含まれ、繊維が多いということで健康に良いとか。
またケーキの材料としても知られるようになり、ケーキ屋さんで無花果のケーキをよく見かけるようになった。不思議なことに無花果のケーキについ手が伸びてしまう。
先日、東京のホテルでウエルカムフルーツとして無花果と柿がお皿に載っていた。かつての情景とは少し違っていたが、昔のように白い樹液を避けながら一つ口に入れた。素朴で懐かしい味だった。
無花果の暗き深紅を煮つむべし 黒田杏子
(児島医師会報 2009.11月号掲載)