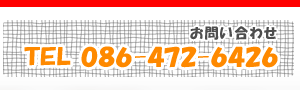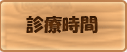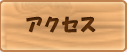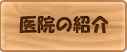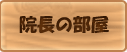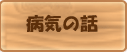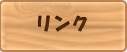クマゼミ
夏の朝はクマゼミの合唱で始まる。カーテンをすり抜けるひんやりとした風がもたらすひとときのさわやかさは、セミたちの声でかき消される。暑く悩ましい一日が始まるのだ。
ときおりの不眠に、早朝から鳴き始めのクマゼミたち、ちょっとまて。
蝉涼し 足らぬねむりを ねむりつぐ (水原秋櫻子)
うるさいけれど嫌いじゃない。セミの鳴かない夏なんて不気味である。
いつの頃からか、家のまわりにはクマゼミしかいなくなった。以前はニイニイゼミやアブラゼミがモミジやサクラの木にとまって、夏を彩っていた。
子どもの頃、麦わら帽子をかぶり、身の丈よりは遥かに長い網を振り回し、セミ達の失笑を買った。岡山にはアブラゼミが多く、その声のつやのなさに生命力を感じていた。汗だくであこがれのクマゼミを探しまわった。僕たちは彼らを"シャーシャー"と呼び、捕れれば神様に感謝した。が、かごにはアブラばかりだった。
朝、新聞を取りに門のところまで出ると、一体何匹いるんだろう、鳴き声が迫ってくる。耳が痛いほど。頭のなかで氷を削っているよう。シャコシャコと共鳴する。
あわてふためいて、僕の頭や顔にぶつかってくる奴がいる。おしっこをひっかけられる。昔はイボができるといったものだ。それにしても本当に飛ぶのがへたである。彼らの羽はその場を逃げるためだけものもののようだ。セミは鳴くことに進化をしてきたのだろう。
クマゼミの傾向だが、あまりに低い枝にとまるので、幼い女の子に簡単に捕まっていた。日本最大で、セミの王ともいえないほどのていたらくである。今時の子どもたちは見向きもしない。
しかし、なぜこんなにクマゼミばかりになったのだろう。
関東地方が北限で都市化が進んでいるところは、アブラゼミより多いともいわれている。大発生する傾向があり、おそらくは他のセミより地球温暖化に適応していると思われる。日本はそのうちクマゼミばかりになるかもしれない。 いやいやながら捕まえたアブラゼミはどこへ行ったのだろう。ニイニイゼミもいない。ツクツクホウシはもう少し後の季節か。秋が近くなると、山の近くで寂しげにヒグラシが鳴き始める。待ち遠しい気もする。
松尾芭蕉の「閑けさや 岩にしみいる 蝉の声」の蝉は何かということで、斎藤茂吉らが論争したという。結局、この句は7月中旬、立石寺で詠まれたことからニイニイゼミであろうということになったそうだが、200年以上前のことでもあり断定は難しいと思われる。
句の情景を思うとクマゼミの声も悪くはないが、やはりうるさすぎるか。いずれにしても西のセミであるクマゼミの出番はない。ヒグラシの声なら雰囲気がぴったりなのだが。
遠ざかる クマゼミの声 高き空
また夏が行く。
(児島医師会報 2005.8月号掲載)