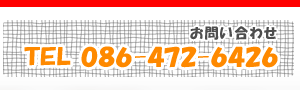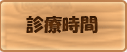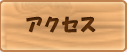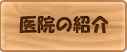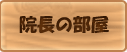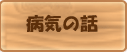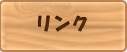湿原の涙

ラムサール条約にて定義する「湿地」とは湖沼、浅い海から水田や養殖池まで水に係わる場所はほとんど含まれる。つまり水のある土地はほぼ湿地ということになる。日本中に湿地は無数にある。
その昔、人類の生活は湿地から始まり、湿地と共に繁栄してきた。あの楼蘭や滅びた古代遺跡をみれば一目瞭然、人類はどんなに栄えていても水が無ければ生きてはいけない。現在でも水とのふれあいは欠かせない。海水浴、潮干狩りなど水辺での遊びは楽しい。自分の中の“子ども”を呼び起こしてくれる。
 湿地というと釧路湿原が心に浮かぶ。湿原の中を釧路川がしなやかに蛇のように曲がりくねり、時間が止まっているかのような風景。燵ケ岳をバックにした尾瀬沼。人が余り住めないところ、ミズバショウ、じめじめ。その程度の認識。湿地は長い間、開発しにくい不要の土地、日のあたらない谷地、単なるごみ捨て場など日陰者であった。しかし、実はそんな不毛の地ではなかった。
湿地というと釧路湿原が心に浮かぶ。湿原の中を釧路川がしなやかに蛇のように曲がりくねり、時間が止まっているかのような風景。燵ケ岳をバックにした尾瀬沼。人が余り住めないところ、ミズバショウ、じめじめ。その程度の認識。湿地は長い間、開発しにくい不要の土地、日のあたらない谷地、単なるごみ捨て場など日陰者であった。しかし、実はそんな不毛の地ではなかった。近年、湿原の生態系の重要性が世界的に見直され、多様かつ貴重な生物相ばかりでなく、湿地の持つ保水、水の浄化、有害物質の濾過といった環境保全機能が地球レベルで働いているのだという。この条約はこのような湿地の存在意義を知らしめたという点で評価される。
問題は登録すらされなかった湿地が多いこと。日本で「湿地」として登録されたのは、わずか9地域にすぎない。ヨーロッパなどに比べると圧倒的に少ない。これは開発をすすめようとする行政の思惑があるからだ。特に大都市近郊の干潟は渡り鳥にとって非常に重要な越冬地であるだけでなく、海水の浄化機能が少なからずあることがわかっているにもかかわらず黙殺された。また、登録されていても森林伐採や、農地開発、牧草化、観光化などで破壊が進んでいる。
日本最大の釧路湿原も例外ではない。優雅でたおやかに見える風景は少し周囲を見渡すと遥かに牧草化され、水をせき止めたため乾燥化が著明で、また境界領域は広大なごみ捨て場と化しているという。ゴルフ場開発もご多分にもれず釧路川流域で計画中のものを含めると18ヶ所もあるという。丹頂の舞うような湿原で何もゴルフをすることはなかろう。そしてあのセクシーでさえある流域が治水工事とやらでまっすぐにされているそうだ。湿原はまさに泣いている。
 フンボルトワッサーは直線は自然のものにはあり得ないといったが、正に排水路と化した釧路川は悲しい。もともとラムサール条約は渡り鳥の保護のために作られたものである。湿原や干潟は渡鳥の飛来地、生息地として大変重要である。ヨーロッパで渡り鳥をいくら保護しても、飛来地が破壊されていれば意味がない。そして鳥たち以外の貴重な生物種のためにも同様である。彼らの生存に必要な湿地はどんどん消失してゆく。一度失われたらもう元に戻らない。湿地のような物言わぬ、か弱いところには開発の手が簡単にのび、名も知れぬ小さな生き物や水鳥たちはその犠牲になる。もうここらで考え直してもいい頃ではないだろうか。
フンボルトワッサーは直線は自然のものにはあり得ないといったが、正に排水路と化した釧路川は悲しい。もともとラムサール条約は渡り鳥の保護のために作られたものである。湿原や干潟は渡鳥の飛来地、生息地として大変重要である。ヨーロッパで渡り鳥をいくら保護しても、飛来地が破壊されていれば意味がない。そして鳥たち以外の貴重な生物種のためにも同様である。彼らの生存に必要な湿地はどんどん消失してゆく。一度失われたらもう元に戻らない。湿地のような物言わぬ、か弱いところには開発の手が簡単にのび、名も知れぬ小さな生き物や水鳥たちはその犠牲になる。もうここらで考え直してもいい頃ではないだろうか。自然にあるものでその存在が不要なものなど何もない。私たち人間にとってとるに足らないものと考えられたものが、実は非常に重要な働きをしているという事例は枚挙にいとまがない。最後はまわりまわって自分たちに返ってくる。私たちの子どもや子孫に。
(1992.6)
(写真は後藤昌美さん撮影のものです。)