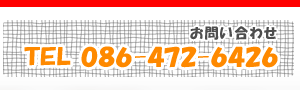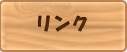かつて極めて小さな未熟児は生存することはなかった。しかし医学の進歩により、かなり小さな未熟児が助かるようになってきた。
小児科医になって3年ほど経った頃、在胎24週くらいだったろうか、大人の掌よりほんの少し大きいくらいの生まれたばかりの未熟児が小さな木の箱に入れられてきた。500gくらいだっただろうか。息もたえだえであったがまさに人間の形をしていた。いあわせた産科の医師は静かに背を向けた。こういう時代であった。
大学でもひとつめの研修病院でも未熟児をみたことがなかった私はその、今にも壊れそうな小さな体となおも生きようと微かに動く指先を驚愕の念をもって見つめていた。これは無理だ、生きられるわけがない、そう思った。その子は私にとって死に瀕した、恐ろしく小さな生き物であった。
後に未熟児をケアするようになったが、その子を救えたかどうかわからない。
しかし、もし当時の最も進歩したNICUならば助けることができたかも知れないと思うようになっていた。というのも未熟児学の進歩はすばらしく、経皮酸素モニターを始め、1分間に400回もの呼吸数を設定できるレスピレーター(最近のものはさらに高頻度のものが登場している)の出現、輸液の技術(静脈カテーテルの進歩と1時間1cc程の輸液)の進歩、各種薬剤、さらに人工の肺界面活性物質の登場に加えて輸送システムの整備、未熟児スタッフの専門化などによって1000g以下の児は言うに及ばず、600g以下の児でも助かるようになってきたからである。
かつて脳性麻痺の3大原因のひとつに数えられていた未熟児に対する医療は、新しい局面をむかえている。 従来の生命を助けるという医療から、さらに進んで intact survival (後遺症のない生存)をめざしているのである。確かに、超未熟児に多い重症黄疸、肺疾患、感染症、腸疾患、未熟児網膜症など克服されてきてはいるが、児が小さくなればなるほど頭蓋内出血、その他合併症の頻度は高くなり、生存すれば後遺症は当然増加してくる。
いくら減少したといっても、軽度のものを含めるとまだかなりの率で後遺症が認められる。とくに神経学的後遺症が重要である。現代のような子どもの少ない時代の諸事情を考えると、後遺症を持ったこどもの一生にわたる家族並びに本人の社会的、精神的負担は大変大きいと思われる。
未熟児ができる原因のひとつに母親の年齢がある。多くの未熟児の母親は極端に若いか、妊婦として高齢かである。どちらも母体として問題があるのである。
しかし、社会的、生物学的にその意味は大きく異なる。若い母親は比較的ドライで、失敗したという感覚が強いように思える。児に対しても助からなくても良いような気持ちを持っている印象を受けることがある。
それに対して高齢出産の母親はなんとか助かってほしい、そして自分が悪かったのだと自らを責める気持ちが強いようだ。これからも子供が生めるか、もうこれが最後かという違いであろうか。
父親にしても同様である。夜を徹してクベウス(保育器)にまさに張り付いているとき、親のそんな感じがいたいはどわかる。深夜、未熟児の処置をしていると、ふと白髪まじりの父親が柱の陰の方で心配そうに子供をのぞいていたことがあった。こういう時なんとか元気に生かしてやりたいと思うのだ。
わたしたちがケアした最も小さな未熟児は在胎26週、出生時体重564g、父親が38才、母親が37才で、すでに3回流産をしていて、おそらくこれが最後のチャンスと思われた。もちろん子供はいない。出生時564gと聞かされたとき二人は諦めたようだった。木の箱に入れられないまでもしばらくそのままにされていたのだ。それはかつて私がみた光景だった。けれどもこの子は自分で呼吸をし、よく動くので私の勤務していた病院に搬送されてきた。低体温に陥り呼吸もかなり弱っていたが保温と短時間のレスピレーターケアでしっかりとした呼吸をしはじめた。
母親はやつれはて、しばらくは恐くて未熟児室に来ることができなかった。
経過は黄疸や腸炎、敗血症をおこしかけたりしながらも、何ども危機を乗り越え、46日間の輪液、5ヶ月のクベウス生活の後、生後6ヶ月3Kgとなり後遺症なしで元気に退院した。我々スタッフは苦難の連続ではあったが、このときの両親の笑顔は今でも忘れられない。この子はとても小さかったが、生きる力があったのだとおもう。我々はそれに力を貸したにすぎない。この子は今、6才になるはずだが、元気に育っているらしい。
未熟児ケアしていたときいつも考えていたことは、この目の前の未熟児が助かるのか、後遺症なしで育つのか、生命だけは助かっても脳性麻痺になりはしないか、ちゃんと学校へ行けるくらいになるだろうかということであった。体重は大きくてもあきらかに重篤な頭蓋内出血を起こしていると思われる児は、ほとんど確実に脳性麻痺になる。脳死に近い状態で、1年以上レスピレ一夕ーに支えられて生きていることも希ではない。
そこまで重篤でなくても、将来悲観的に見える児の横で苦悩しながらも、児の状態が悪化すればつい手が動く。何か処置をするはうがよはど楽だから。
悪性腫瘍の末期の患者などのケアと似ているが、事によると何十年後にまで問題が持ち越されるところがまったく違う。やはり未熟児は元気で生きようとしている児が助かるべきなのだろう。
Neonatologist(新生児科医)の仕事は未熟児を助けることでなく、生きようとする未熟児に手をかすことだと思う。超未熟児を助けようとすること自体、自然淘汰に反しているような気もするが、生まれたからには、どんな小さな児でも生を楽しむチャンスを与えてやりたいと思う。
とてもしんどい仕事ではあったけれど、苦労に苦労を重ねて2キログラムほどになった児が初めて自分の口からミルクを飲んでくれたときの喜びは他にかえがたいものがあった。 そんな喜びがなければ未熟児を扱う仕事はとてもできない。静謐な未熟児室には泣き声はほとんど聞こえず、レスピレーターだけが乾いた音をたてている。
けれどそこには未熟児たちの微かな動きの中に生命の輝きと喜びがあふれているのだ。その中では今このときも生死をかけた静かな戦いが続けられている。かつては木の箱の中で死を待つだけだった小さな子が成長し、幸せな人生を歩むことができることを祈る。それが、今は未熟児室に入ることもなくなってしまった私にできるただひとつの事である。
(90.7)