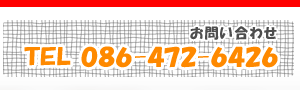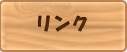柳
小学生の頃だったろうか。家の近くに幅が4メートルほどの小さな川があり、畔に1本の柳が生えていた。ところで、僕の認識では柳といえばしだれ柳と相場が決まっていた。生まれ故郷の倉敷川のほとりには十数本のしだれ柳が優雅に美しい青葉をたゆらせている。涼しげな表情が目に優しい。川と調和している。
やはらかに柳あをめる
北上の岸辺目に見ゆ
泣けとごとくに
(啄木)
どうもしだれ柳とは違うようだ。記憶の中の柳の木は小さかったし、川の中に伸び上がるように、風に刃向かって枝を踊らせていた。たぶん川柳(かわやなぎ)という種なのだろう。川辺のぬかるみに足を取られながら、枝を小さなポケットナイフを使って苦労して切った。見上げると夕日がそこにあった。
しなりがある。柔らかく子どもの手でも切ることができた。小さな鞭をつくるためだった。足元の草をなぎ払ったり、切ったり、カエルやヘビと格闘するためである。大切な武器だった。それにどこからか竹の割れたものを取ってきて、丹念に削り、刀をつくった。万全だった。川の周りには葦やいろいろな草が生えていて僕を待っていた。足元の川にはメダカやドジョウがいた。カエルがあざ笑うかのようにけろけろ鳴いていた。
あるとき、友達とこの小さな川でいかだづくりをして、遊んだ。いかだは近くにある丸太を縄で縛って、畳1畳半ほどにしたものを作った。なぜか丸太があった。それを友と川岸に運んで乗った。さながら、いかだ流しのように長い木の棒を使って、流れに任せ、悦に入っていた。そのとき、川のそばを歩いていた青年が僕たちを注意した。「危ないからよせ」というようなことをいったと思う。ぶつくさ言いながら、僕たちは引き上げた。足が十分つくような川だったから。
あのときの友は今どこにいるのだろう。誰かも思い出せない。
その後も、静かに川は流れていた。しかし、あの柳はなかった。川がコンクリートで固められ、そのときに切られたのだろう。川面に映るきりりとした柳の枝は彼方に行ってしまった。夕日も周りに家やビルが建ち並び、川面に映ることはない。 (1999.9)